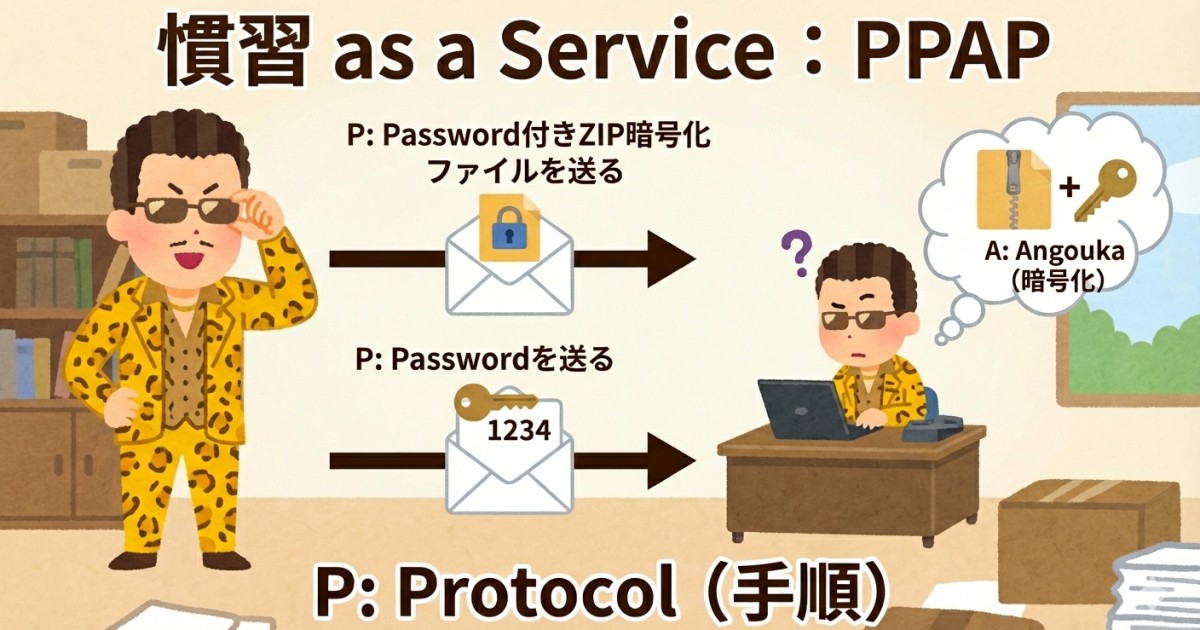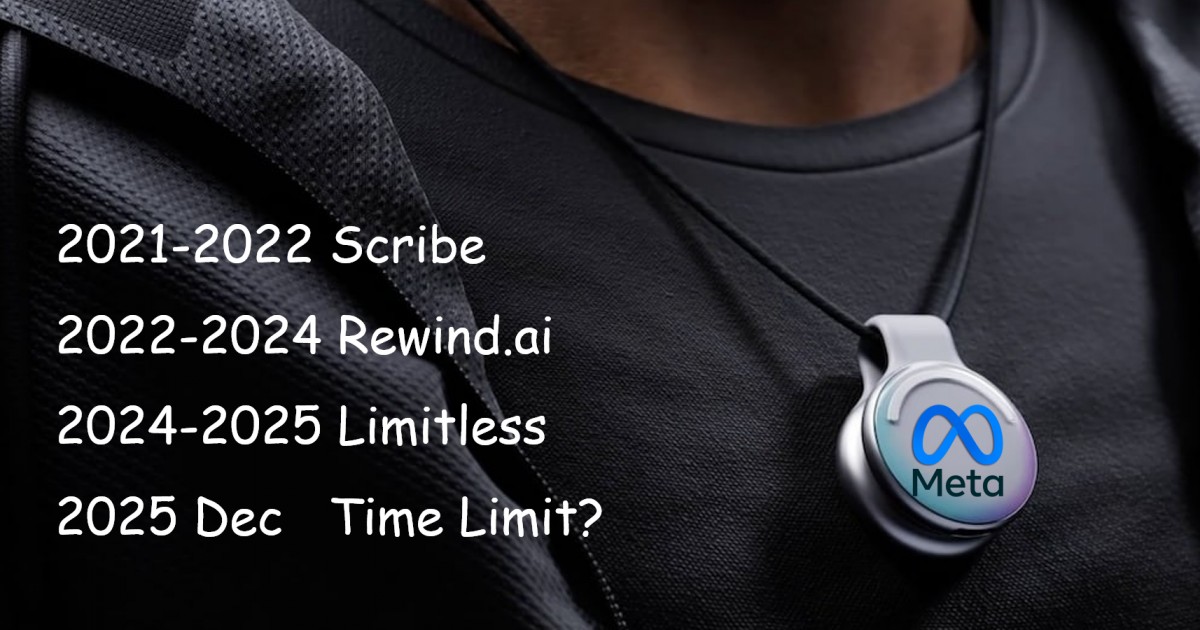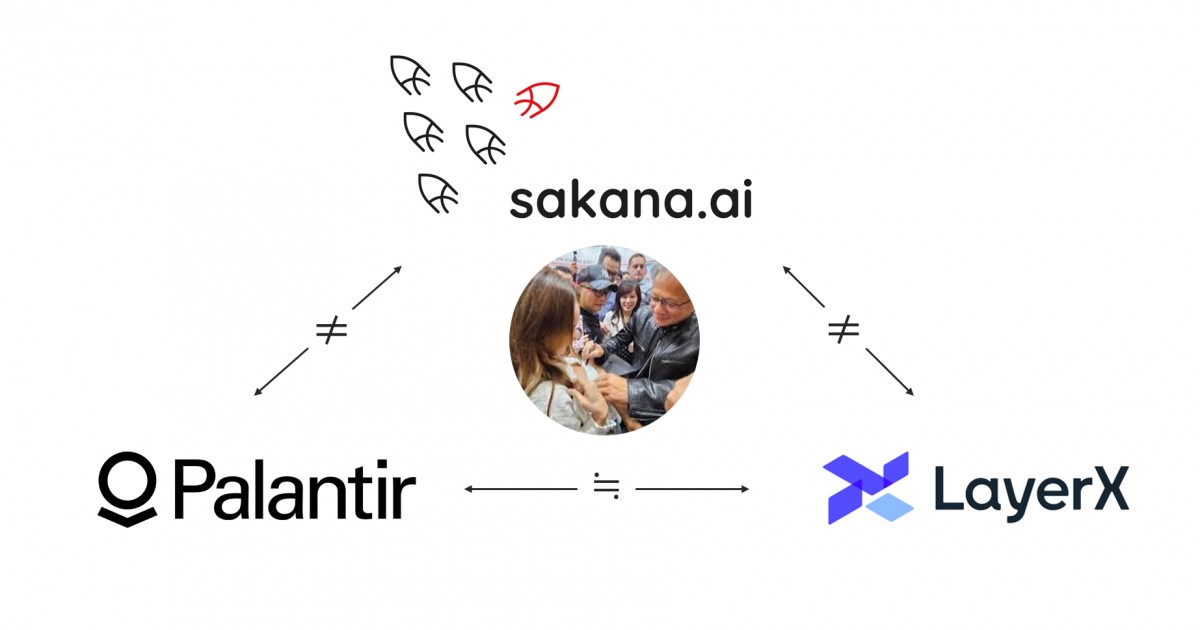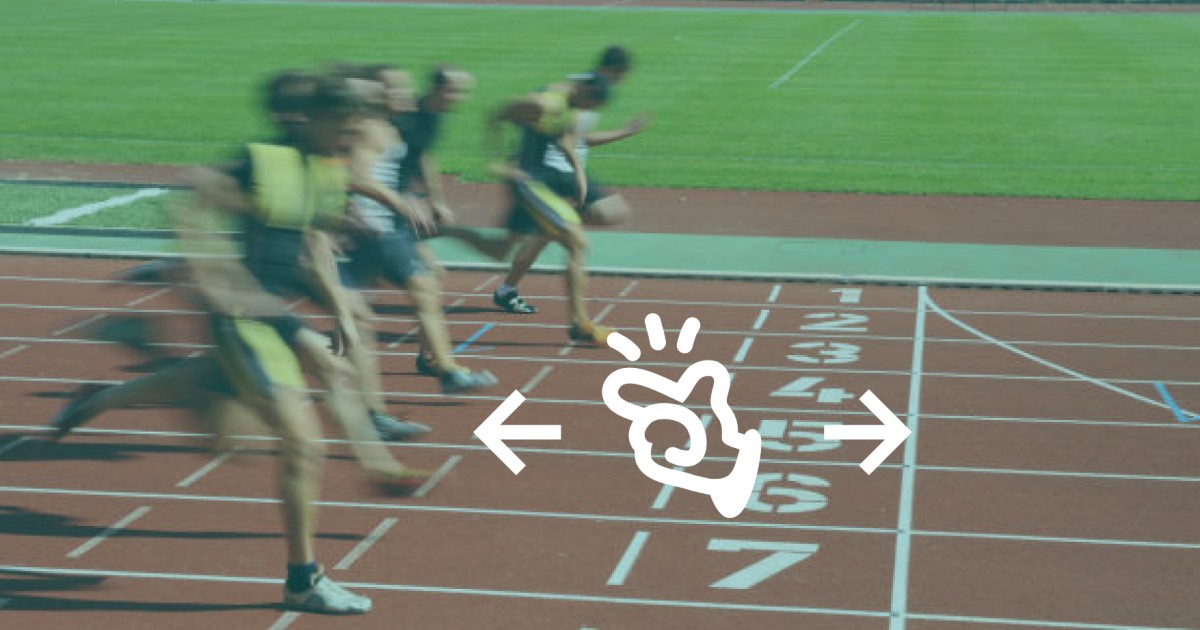DeepSeekとハッカー魂
前回DeepSeekに言及してからまだ1週間である。
しかしそこからNvidiaの市場価値が90兆円蒸発、DeepSeek as a ServiceがAWSに爆誕、OpenAIは出し惜しみしていたo3-miniを無料公開、Anthropicの社長の書いた「DeepSeekはそこまで脅威じゃないけれど、輸出規制は大事よ(ってどっちやねん!)」(AIを使わずに独善的に意訳)という内容のブログが物議を醸したりと、目まぐるしい七日間となった。
ハッカー特色的DeepSeek
トピックが多すぎてどれから分析すれば良いのか迷ったのだが、「ハッカー精神の代弁者としてのDeepSeek」という切り口で考察してみたい。ハッカー精神の本質、そしてそれに相対するOpenAIとAnthropicの反ハッカー精神を考察することで、この短期間にDeepSeekがもたらした技術的・社会的・政治的・経済的変革が一つの線でつながると考えるからだ。
今回のDeepSeekに関する考察において大事な点は4つある。AIとは直接関係のないシステムプログラミングの領域でも技術的進歩があったこと、ソフトウェアとして無償公開されたこと、思考プロセス(Chain of Thought)を公開したこと、そして最後にOpenAIの利用規約に反したかたちでOpenAIから教師データを手に入れた可能性が高いことだ。
この4つの特徴に共通しているのは、どれもハッカー精神を体現しているという点だ。ここでいうハッカーというのは、情報システム侵入など悪意ある行為のことではなく、コンピュータに熟知しており、その豊富な見解を活かして独創的なプログラミングに従事する者たちを指す。Paul Grahamが『ハッカーと画家』の中で語ったハッカー像である。
先ずシステムプログラミングの領域での技術的進歩であるが、特に話題になったのが、Nvidiaが開発者向けに提供しているより抽象度の高いCUDAではなく、その一つ下の下の抽象化レイヤーに位置するPTXの中間表現を直書きすることでパフォーマンスを改善した話だ。輸出規制がある中H100劣化版として中国に輸出されていたH800の性能を活かしきるためだと言われており、限られた物理的資源の中でGPUの知見を総動員し効率化したことは、まさにハッカーの所業だろう。