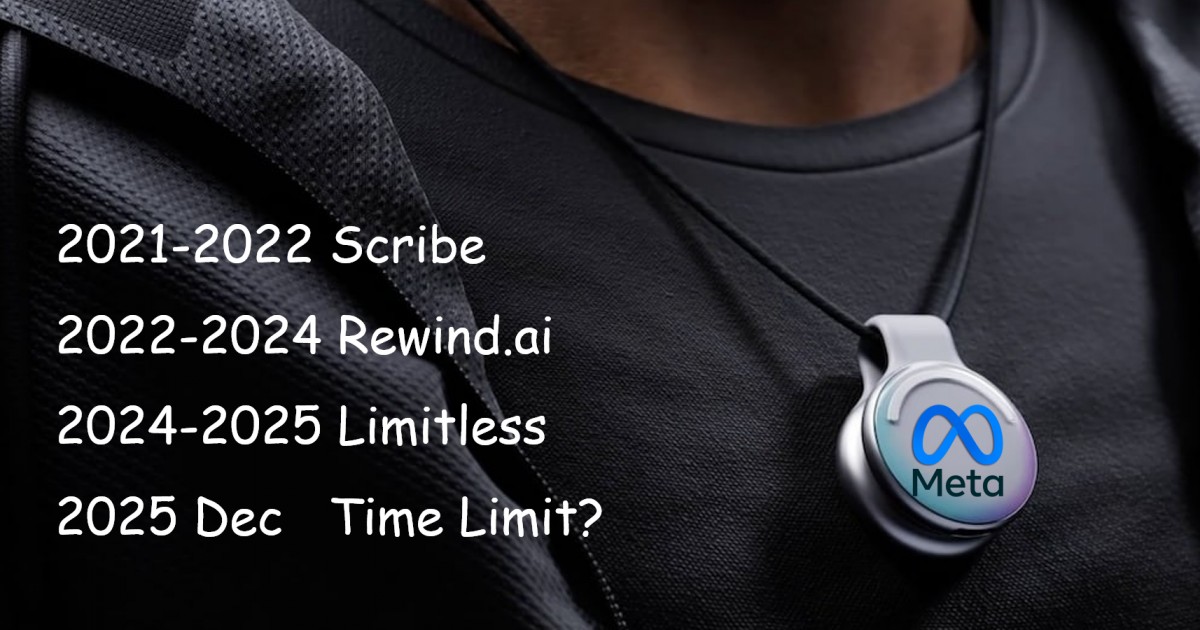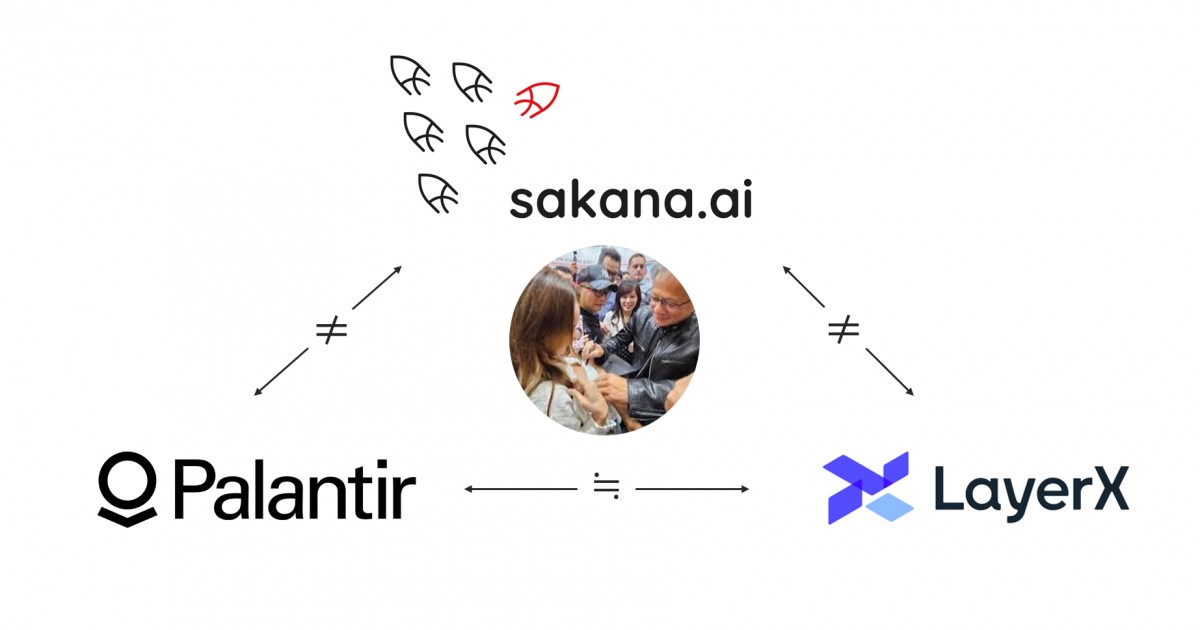LLMがオワコン化した2024年
2024年中に総括を書く時間がなかったので、2025年の初稿は2024年の総括から始めたい。
当ニュースレターは2023年を「SaaSがオワコン化した年」と位置づけたが、2024年は早くもAIが終わった一年であった。少なくとも大規模言語モデル(LLM)そのものの発展を、物珍しそうに追いかける時期は過ぎた。生成AIが今後どこまで賢くなるかはもちろん未知数である。しかし、既に業務で十分に役立つレベルにある現行モデルのコストが今後も下がっていくことは確実だ。

For AI application companies, cost of "intelligence" is falling significantly faster than compute and storage fell for SaaS a decade ago.
ちょうど先週、中国の生成AIスタートアップDeepSeekがGPT-4o相当のパフォーマンスを10分の1のコストで実現するDeepSeek v3を発表した。そもそもGPT-4oが発表されたのが5月なので、たった半年で90%のコストダウンを実現したということになる。生成AIとて所詮はソフトウェアであり、その複製コストはやはりゼロに近づいていくようだ。
呼び出すか、呼び出されるか
そういうわけで、2025年は生成AIのコモディティ化がさらに進むだろう。SaaS企業に限定するのならば、それはAIを呼び出すこと、そしてAIから呼び出されることの双方を前提とした戦略を組むことを意味する。
まずAIを呼び出す方だが、こちらに関しては既に各社とも動きが早い。これまでのSaaSはどれも究極はデータベースのラッパーであった。しかしLLMの登場により、データベース内に格納された独自のデータを、LLMが内包するいわゆる「常識」で補完することがいとも簡単になった。
最近のCRMには顧客情報を元に自動的にメールの文面を作成してくれる機能がついていたりするが、これも顧客DBという固有の情報と、良識ある社会人が身につけているだろう書き言葉という常識を掛け合わせているに過ぎない。そしてなぜこれに価値があるかというと、人間の社員が社会人としての良識を持ち合わせているとは限らず、たとえ持っていたとしても、AIの方がテキスト生成が速いからである。ホワイトカラーとはすなわち特定文脈を理解している一般人であり、そのデジタル的量産の手はずは整ったと言えよう。
これまで深く理解されてこなかったSaaSの提供価値の一つに「顧客のビジネスニーズに即したかたちでデータベースとそのスキーマを選ぶ」というものがある。世の中にはいろいろなデータベース技術が存在し、同じ技術でも設定次第で性能特性は大きく変わるので、いざ業務アプリケーションを作るとなると、ニーズに即した選定と設計が必須となる。SaaSベンダーはこれまでこの部分の抽象化を一手に引き受けてきたのだが、今後似たような役割をLLMに於いて担う必要がある。エンドユーザーからすれば、各LLMが何が得意で、どう使ったらコスパが良いかを調べるのは必ずしも容易ではない。この部分に関してSaaS企業が専門性を持ち、顧客から既に預かっているデータを有効活用することで、特定のタスク群に対してChatGPTのような汎用的AIアプリを超える性能を提供できる可能性は十分にある。
SaaS企業からすれば、モデルレイヤー各社の鍔迫り合いは続いてもらった方が嬉しいはずである。データベースラッパー改めデータベース&LLMラッパーとなっていくSaaSからすれば、特性を持ったモデルが多数ある方がモデルソムリエとして提供できる価値が大きくなるからだ。逆にもしモデルレイヤーでの淘汰が進み寡占的市場となるとしたら、モデル提供元自体がSaaS化し直接的競合となっていく可能性が十分にある(OpenAIの方向性はまさにこれである)。
次にAIから呼び出されるサブシステムとしてのSaaSについて考える。これまでSaaSは第一に人間、第二にプログラムに呼び出されることを想定して設計されてきた。人間のためにまずUIを提供し、利用パターンがそれなりにかたまったユーザーが、一部その利用方法を自動化できるようAPIを提供するというのが、SaaSインターフェース開発の定石だ。もしAIが直接SaaSを使うようになるとすると、一体どのような変化が起こるのだろうか。
まず確実に言えるのが、呼び出される側にまわるSaaSの競争力は下がる。AIからすればSaaSに求めるのはデータと文脈の提供でしかないので、それはAPIさえあれば十分であり、今後画面操作機能が向上し画像認識の精度が向上するならば、APIがなくてもデータを引き抜けるようになるだろう。AI側の労働力は安くなっていくので、「このSaaSはベンダーロックインの可能性があって怖いので、すべてのデータを引き抜いてください」みたいな指令を出すことで、APIがなくてもデータ移行が実行できるような未来も十分に想像できる。同じAPIでも、Application Programming Interfaceではなく、Agent Person Interactionの方が重要になっていくのではないか。「データの重力がMoatとなる」というSaaSの定説がひっくり返る可能性も否定できない。
そんなわけでSaaS企業たちはどこも自分たちが他のSaaSを呼び出す側に回ろうとする。そして他のSaaSを呼び出せる立ち位置を確保するためには、人間様に直接ログインしていただけるサービスであり続ける必要がある。これこそ昨年SaaS業界人が口を揃えてUX至上主義を叫び始めた要因だ。
実際にどのような変革が考えられるだろうか?SaaSに限るのであれば、「パソコンのために人間ががんばらなくてよいパラダイムを作れるか」が大きな論点となるだろう。SaaSは所詮データベースのラッパーだと前段で述べたが、そのデータベースにデータを入力する役割を果たしてきたのは人間である。もしこの面倒で効率が悪いプロセスを取り除くことができるならば、そのサービスは顧客接点を守ることができるようになる。
Agenticナンチャラを巡る攻防
SaaSがメジャー化したことで、複数のSaaSツールを使いこなして仕事をすることは今や当たり前となった。しかしこれは人間が常にコンテクスト変換をし続ける「非常にがんばっている状況」でもある。コンテクスト変換コストを下げる安直な解決策は、人間の代わりにAIにSaaSを使わせることである。これがAgenticナンチャラの本質だが、より叙述的に「SaaS利用代行AI=SaaS Proxy as a Service=SPaaS(笑)」と呼ぶことにする。
SPaaS提供元は二種類考えられる。ひとつは独立した第三者ツール、もうひとつは既にSaaS製品を持っている企業だ。後者からすれば、前者が台頭してくると顧客との直接接点を奪われることとなるので、積極的に競合製品を提供してくるだろう。SalesforceのMarc Benioff CEOは今年のDreamforceでAgentCloudという新概念を提唱し話題となったが、あれも本質的には旧態依然とした製品UXとエンドユーザーの間に競合他社を介在させないための守りの一手と解釈するのが自然である。
ではどのSaaS企業のSPaaSに優位性があるのだろうか。ここでも二つの種類の優位性が考えられる。一つはAdobeやSalesforceのように既に幅広い製品ポートフォリオを有している企業、もう一つはServiceNowのように既存ワークフローを押さえている企業だ。
SaaSポートフォリオを持つ企業にとって、これまでの最大の課題はポートフォリオ製品間の連携であった。どこもM&Aによってポートフォリオを拡充してきたため、いわば「サービス名称だけPMI済み」の状態にあり、サービス間の技術的連携はお世辞にも円滑とは言えず、コンサルティングファームやSIerの協力なくしては成り立ってこなかった。SPaaSがこれらの人的資源を100%置き換えられるとは思えないが、自動化の余地は十分過ぎるほどある。これは提供元SaaSからすれば、当たり障りないかたちで実装パートナーから顧客予算を間接的に奪取できることを意味する。顧客からしても実装・運用フィーが下がることとなるので、悪い話ではない。一方でSIerやコンサルテイング会社は、アーキテクチャ設計プロジェクトはともかく、運用プロジェクトのあり方については抜本的な見直しを迫られるだろう。
既存ワークフローを押さえているSaaS企業にとって、SPaaSは渡りに船である。なぜならワークフローを押さえているということは、SaaSを利用した業務のどの部分が自動化されていて、どの部分が属人的か把握できているということであり、属人的ホワイトスペースを埋めるためにSAaaSを有効活用することができるし、なんならそこを起点としてTAMの拡大を狙うことができる。顧客企業からしても、既に社内業務の自動化を担っているベンダーが、さらなる自動化を推進するというのはわかりやすい。元々ワークフローという横断的切り口でビジネスをしているので、SaaSポートフォリオ企業のように「自社ツール間のSPaaS連携を社内事情から優先してしまい、各社ツールが混在している顧客が持っているニーズを見過ごす」心配もない。SalesforceやAdobe、Microsoftのようなポートフォリオ企業にとってSPaaSの提供は守りの要であるが、ネイティブSPaaS企業やワークフローSaaS企業にとっては攻めの一手となり得る可能性がある。異質性を許容したbest of breedと均一性を重視するall in oneのせめぎ合いは、今後さらに顕在化するだろう。
昨年はたいへんお世話になりました。2025年もよろしくお願い申し上げます。
すでに登録済みの方は こちら