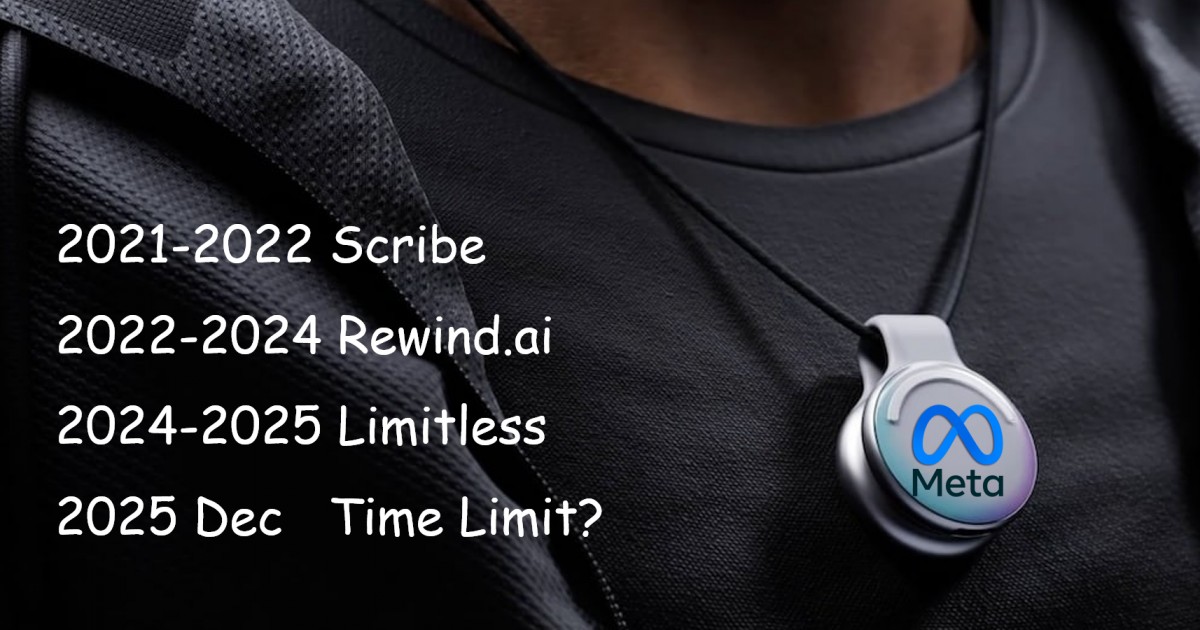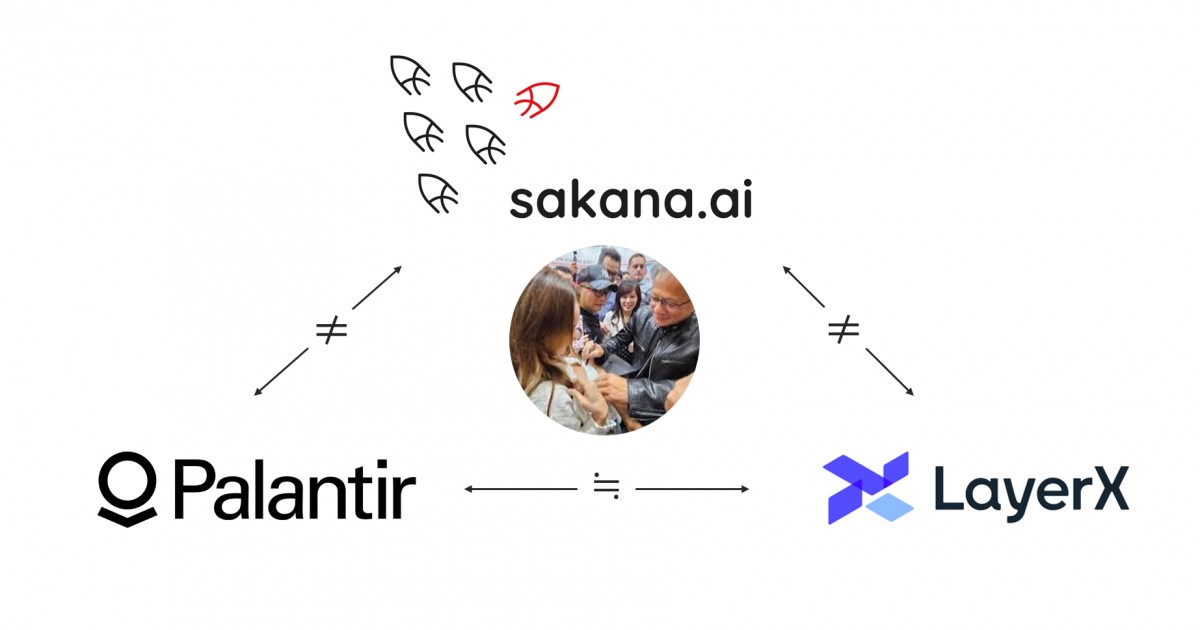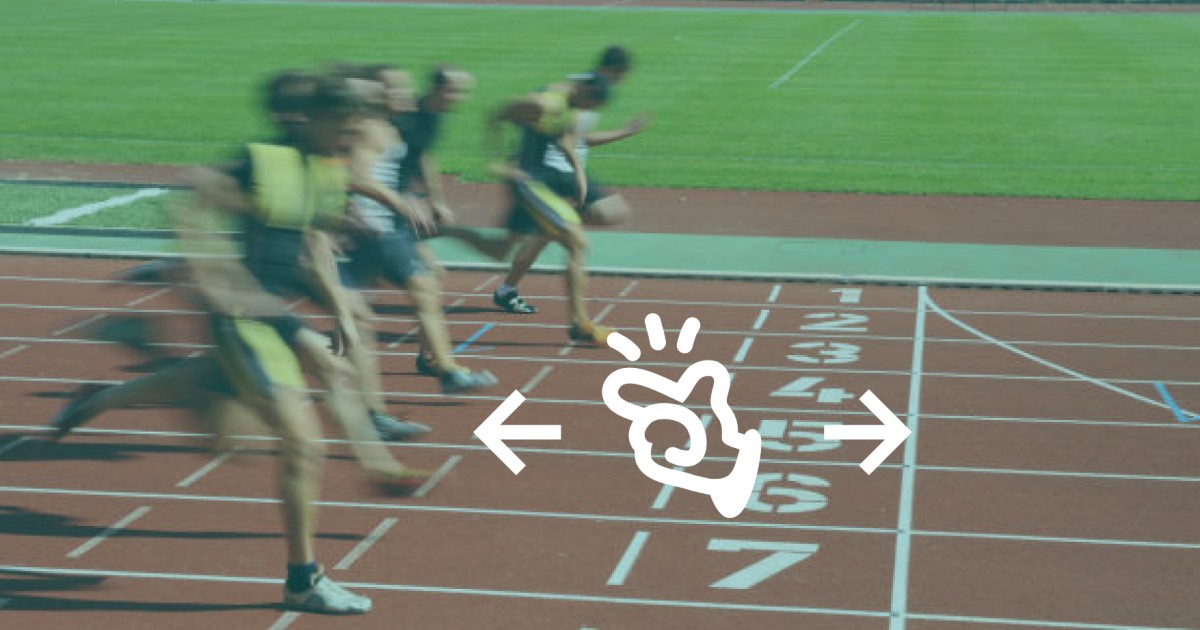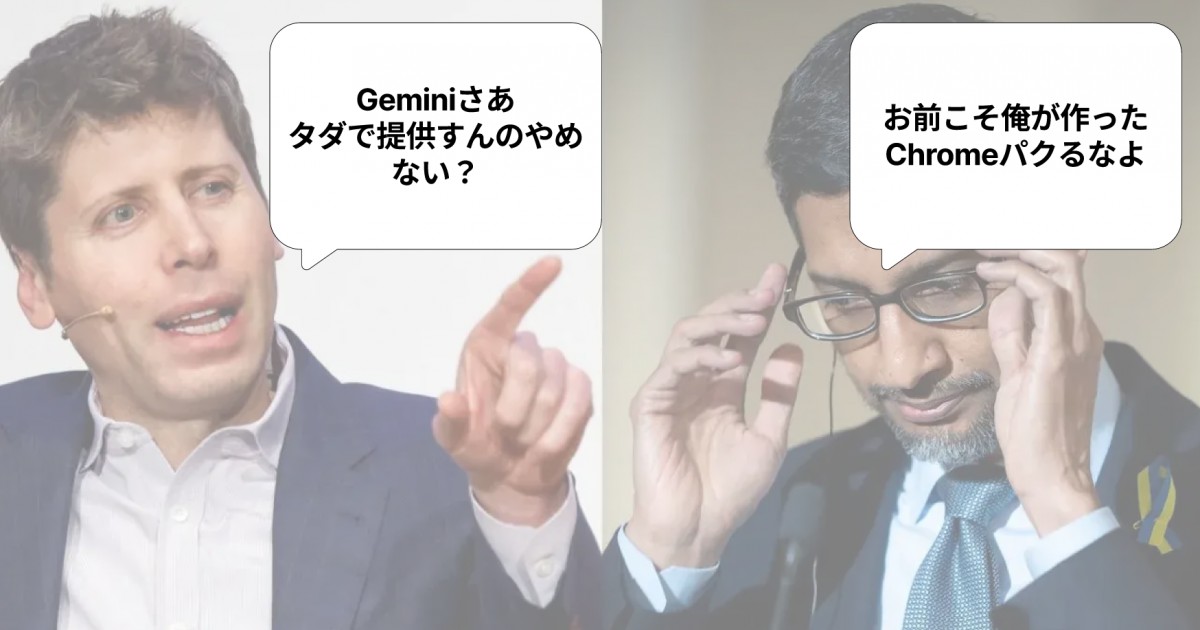最新業績報告まとめ:MongoDB Live 2022

tamuramble.theletter.jp/posts/a917aff0… MongoDB:オープンソースの隠れた巨人 次世代のOracleか、あるいはクラウド過渡期のスキマ商売か? tamuramble.theletter.jp
不況を尻目に積み上げるはデータ基盤ワークロード
今月は米国連邦準備銀行を筆頭に各国中央銀行の話題で持ちきりで、うっかり見落としていたのだが、月初にMongoDBの四半期業績報告と、一年に一度のイベントMongoDB Liveがあった。三年ぶりに対人での開催となったMongoDB Liveは戦略的にも技術的にも盛りだくさんの内容で、市況の先行きがあやしい中でも、明確な方向性を打ち出すものだった。今週はMongoDB Liveの内容を振り返りながら、今後のMongoDBの戦略を分析していきたい。
今年のMongoDB Liveを一言で総括するならば、獲得可能市場規模(Total Addressable Market≒TAM)の拡大だ。投資家向けセッションのこちらのスライドが、彼らの戦略を端的に表している。

https://app.socio.events/MTI5Mzc/Agenda/211614/Session/612854 から抜粋(00:02:14-00:03:14)
MongoDBに限ったことではないが、特定の業務ドメインを一手に引き受けるSaaSと違い、その下に入る(データ)プラットフォームが注力すべきは更に細かい粒度であるworkloadであり、いかに隣接するworkloadを特定し、その処理を自社プラットフォームに移管させるかがTAM拡大のカギとなる。
新規アプリのお手軽データベースというworkloadから出発したMongoDBだが、2017年の上場以降、着実に新しいworkloadを付け加えてきている。2019年にはモバイル端末データベースを提供するRealmを買収、2020年にはAtlas Search(検索)とAtlas Data Lake(分析ストレージ)、そして今年のMongoDB Liveではカラム型インデックス採用も発表、分析用途にも本格的に踏み出している。
こうやって羅列してみるととりとめがない製品群に映るが、そこには一つの共通点がある。それは開発者がウェブサービスやモバイルアプリを作る際、必要となるデータ周りの機能を一つずつ抑えていっている、ということだ。
この戦略的視点が詰まっているのがChief Product Officer(CPO)であるAzam氏のプレゼンに出てくる架空サービスLeafyだ。